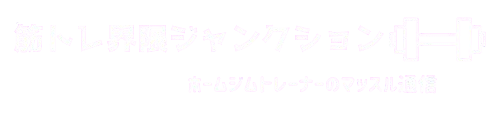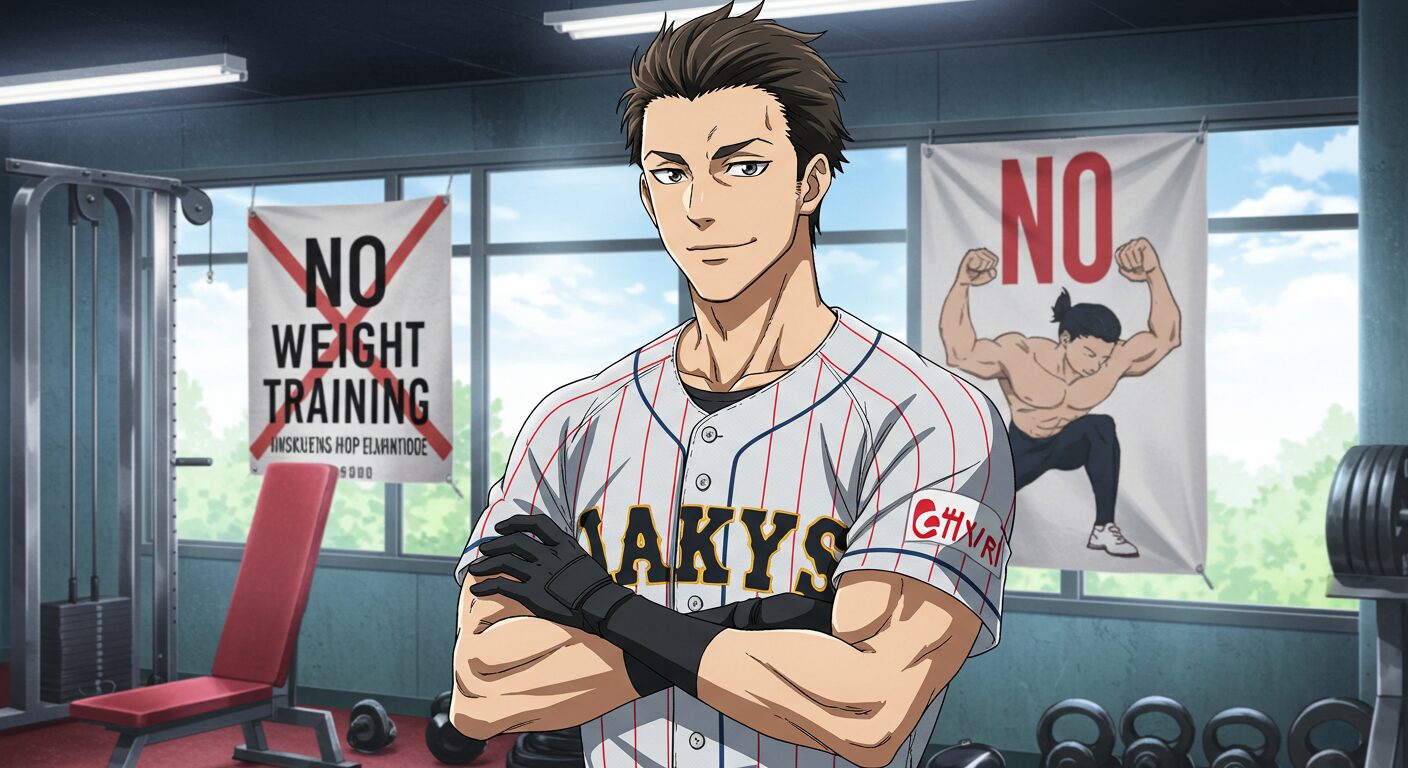「イチローは筋トレをしない」——この噂を聞いたことがある人は多いでしょう。しかし、本当に彼は筋トレをしていないのでしょうか?また、筋トレをしなくても一流のパフォーマンスを維持できた理由は何なのでしょうか?
この記事では、イチローの公式発言や実際のトレーニング内容をもとに、「筋トレをしない」と言われる背景を詳しく解説します。また、筋トレをしないことで得られるメリットや、競技によっては逆効果になり得るケースについても触れていきます。
さらに、イチローが実践している「初動負荷トレーニング」の具体的な内容や、筋トレなしで競技力を向上させる方法についても紹介。あなたの競技や目的に合ったトレーニングの選び方がわかるはずです。ぜひ最後まで読んで、自分に最適なトレーニング方法を見つけてください。
イチローは本当に筋トレをしていないのか?

イチローの公式発言:「筋トレしない」は本当か?
イチロー選手が「筋トレをしない」という話はよく語られますが、実際にはどのような発言をしているのでしょうか?
イチローはこれまでのインタビューやドキュメンタリーで、「ウェイトトレーニング(=重いダンベルやバーベルを使った筋力トレーニング)はやらない」と語っています。例えば、2009年に出演したNHKの特集番組では「筋肉を大きくすることは自分のプレースタイルに合わない」と明言しています。また、2018年の引退会見でも「自分に必要なのは柔軟性としなやかさ」と語り、筋肥大を目的とした筋トレを避けてきたことを示唆しています。
ただし、「筋トレをまったくしていない」というわけではありません。イチローは初動負荷トレーニングを取り入れており、これが一般的なウェイトトレーニングとは異なるため、「筋トレをしない」と誤解されることが多いのです。
実際のトレーニング内容|初動負荷トレーニングとは?
イチローが実践している初動負荷トレーニングとは、通常のウェイトトレーニングとは異なり、軽い負荷を用いて関節の可動域を広げることを目的としたトレーニング法です。この方法を開発したのは鳥取県にあるワールドウィングの小山裕史氏で、イチローは1990年代後半からこのトレーニングを継続しています。
初動負荷トレーニングの特徴は以下の通りです。
-
軽い負荷で関節の可動域を広げる動作を繰り返す
-
速い動きの中で筋肉を活性化させる
-
筋肥大ではなく、神経系の強化を目的とする
例えば、一般的なベンチプレスでは大胸筋や上腕三頭筋を鍛えますが、初動負荷トレーニングでは腕をしなやかに振るための筋肉を鍛え、可動域を広げることを目的としています。これにより、イチローは40歳を超えてもスイングスピードを維持し、高いパフォーマンスを発揮し続けることができたのです。
イチローの体づくりを支えたトレーナーと施設(ワールドウィングなど)
イチローのトレーニングを支えてきたのは、鳥取県にあるワールドウィングエンタープライズとその代表である小山裕史氏です。小山氏は初動負荷理論を提唱し、多くのプロアスリートに指導を行っています。
イチローはオフシーズンには頻繁にワールドウィングを訪れ、専用のマシンを使ったトレーニングを実施していました。これにより、彼は柔軟性を維持しつつ、長年にわたってトップレベルのパフォーマンスを発揮してきたのです。
また、イチローが所属していたマリナーズのクラブハウスには、ワールドウィングの専用マシンが導入され、シーズン中も初動負荷トレーニングを継続できる環境が整えられていました。
イチローが筋トレをしない理由とは?

初動負荷トレーニングが選ばれた理由|筋トレとの違い
イチローが筋トレをしない理由は、自身のプレースタイルに最適なトレーニングを選んだからです。
通常の筋トレ(ウェイトトレーニング)は、主に筋肥大を目的として行われます。一方、初動負荷トレーニングは神経系の発達を促し、動きの滑らかさを向上させることに重点を置いています。これは、イチローが求める「柔軟で素早い動き」と相性が良かったのです。
特に野球では、瞬発的な動きが求められる場面が多いため、筋肉を大きくするよりも、しなやかでスムーズな動きを維持することが重要です。そのため、イチローは一般的な筋トレを避け、初動負荷トレーニングを継続しているのです。
「筋肉を大きくすると動きが鈍る」は本当か?
筋肉を大きくすると動きが鈍る、というのは一概には言えません。競技によっては筋肉量の増加がプラスになる場合もあります。
例えば、パワーヒッターのような選手(アーロン・ジャッジやマイク・トラウト)は、強いスイングをするために筋肉を増やし、それが飛距離向上につながっています。しかし、イチローのような「スピードと柔軟性を活かすプレースタイル」では、筋肉が大きくなりすぎると可動域が制限される可能性があります。
そのため、イチローは筋トレによる筋肥大を避け、動きやすさを維持する方向を選んだのです。
関節の可動域とスポーツパフォーマンスの関係
スポーツパフォーマンスにおいて、関節の可動域は極めて重要です。可動域が狭いと、
-
スイングのスピードが落ちる
-
走る際のストライドが短くなる
-
投球や送球時に肩や肘に負担がかかる といった問題が発生します。
イチローは、長年にわたって柔軟性を維持することで、スイングスピードを落とさず、守備でもダイナミックな動きを続けることができました。そのため、可動域を広げる初動負荷トレーニングが、彼のパフォーマンス維持に不可欠だったのです。
このように、イチローが筋トレを避けたのは単なる好みではなく、彼の競技スタイルや身体能力を最大限に活かすための合理的な選択だったと言えます。
スポーツに筋トレは必要なのか?

「筋トレが逆効果になるケース」|競技別の影響
筋トレはスポーツのパフォーマンス向上に役立つことが多いですが、競技によっては逆効果になることもあります。特に以下のようなケースでは、筋トレが悪影響を及ぼす可能性があります。
①ゴルフや野球などの精密な動作が求められる競技
筋肉をつけすぎると体の柔軟性が落ち、スイングや投球の邪魔になることがあります。例えば、野球のピッチャーが無計画に筋トレをして筋肉をつけすぎると、肩や肘の動きが硬くなり、スピードやコントロールが悪くなることがあります。
②持久力が重要なスポーツ(マラソンや自転車ロードレース)
筋肉が増えすぎると、持久力が必要なスポーツではデメリットになります。筋肉が大きくなると酸素の消費量が増え、長時間動き続けるのが難しくなるためです。例えば、世界的なマラソンランナーであるエリウド・キプチョゲ選手は、無駄な筋肉をつけないように細身の体を維持しています。
③体重制限のあるスポーツ(ボクシングや柔道)
ボクシングなどの階級制スポーツでは、筋肉が増えすぎると体重が増え、不利になることがあります。そのため、ウエイトトレーニングは慎重に行う必要があります。例えば、総合格闘技(MMA)の選手は、筋肉を増やしすぎずにスピードや持久力を維持するトレーニングをしています。
野球における筋トレのメリット・デメリット
筋トレのメリット
-
打球や送球の飛距離が伸びる(メジャーリーガーの多くが筋トレを取り入れている)
-
下半身の強化で投球時の安定感が増す
-
肩や肘の怪我を防ぐ
筋トレのデメリット
-
スイングや投球のバランスが崩れることがある
-
筋肉がつきすぎると可動域が狭くなり、動きが硬くなる
-
筋力が増えても、技術が向上するとは限らない
イチローは「筋肉をつけすぎると自分の動きが制限される」と考え、一般的なウエイトトレーニングを避けていました。一方、大谷翔平は筋トレを積極的に取り入れ、体を大きくしながらも高いパフォーマンスを発揮しています。結局、選手のプレースタイルやポジションに合ったトレーニングを選ぶことが重要です。
ダルビッシュとイチロー|筋トレ肯定派 vs 否定派の比較
ダルビッシュ有(筋トレ肯定派)
ダルビッシュは「筋トレはアスリートにとって不可欠」と考え、体重を増やしながら球速アップに成功しました。彼のようにパワーを重視するピッチャーは、筋トレの恩恵を大きく受ける傾向があります。
イチロー(筋トレ否定派)
イチローは「筋肉をつけすぎると、本来の動きができなくなる」と考え、柔軟性を維持するために初動負荷トレーニングを重視しました。また、「ライオンは筋トレをしない」と発言し、自然な動きの重要性を強調しました。
どちらが正解というわけではなく、プレースタイルに合わせたトレーニングが重要だと言えます。
「ライオンは筋トレしない」説は本当か?

「ライオンは筋トレをしないのにムキムキだ」という話は、筋トレ不要論の根拠としてよく挙げられます。しかし、この理論は本当に正しいのでしょうか?人間と動物の違い、筋肉の発達メカニズム、そしてイチローのトレーニング哲学との関連を詳しく見ていきます。
動物の筋肉の発達と人間の違い
ライオンをはじめとする野生動物は、確かに「ウェイトトレーニング」のような筋トレをすることなく、強靭な筋肉を持っています。しかし、その理由は人間とは大きく異なる生物学的な特性にあります。
遺伝的な筋肉の発達
ライオンやチーターなどの肉食動物は、生まれながらにして筋肉が発達しやすい遺伝子を持っています。特に速筋(瞬発力に優れた筋繊維)が発達しやすく、獲物を捕まえるための筋力が自然に備わっているのです。
一方で、人間は進化の過程で持久力を重視する身体になりました。例えば、持久走では人間は多くの動物に勝てるほどのスタミナを持っていますが、瞬発力や筋力では野生動物に遠く及びません。これは、「遺伝的な筋肉の発達メカニズムが異なる」 ためです。
生活環境と動作の違い
ライオンは狩りをする際、時速60km近いスピードでダッシュし、数百キロの獲物に飛びかかる動作を日常的に行います。この「日常的な動作」自体が、筋肉を鍛えるトレーニングになっているのです。
人間の場合、日常生活ではほとんど筋肉に大きな負荷をかけません。デスクワークが多い現代人は特に、意識的にトレーニングしなければ筋肉が衰えてしまいます。「ライオンは筋トレをしない」ではなく、「ライオンは日常動作がすでにトレーニングになっている」 というのが正しい見方でしょう。
「自然な動きだけで筋肉はつくのか?」科学的視点から検証
「筋トレをしなくても、スポーツや日常動作だけで筋肉は発達するのでは?」という疑問について、科学的な視点から見ていきます。
負荷と筋肉の成長の関係
筋肉は、一定以上の負荷がかかることで成長する という特性を持っています。これを「過負荷の原則」といいます。たとえば、ボディビルダーが筋肉を大きくするために高重量のトレーニングを行うのは、筋繊維に大きな負荷をかけることで超回復を促し、筋肥大を狙っているからです。
しかし、スポーツ選手や一般人が求めるのは、必ずしも筋肥大ではなく「動ける筋肉」です。例えば、サッカー選手やバスケットボール選手はウェイトトレーニングだけでなく、スプリントやアジリティトレーニング(敏捷性向上のトレーニング)を行うことで、競技に適した筋力をつけています。
自然な動きだけで十分な筋力はつくのか?
これについては、「どのレベルを求めるか」によります。
- 一般人が健康維持や適度な筋肉をつけるなら、自然な動作だけでもある程度の筋力はつく
- スポーツ選手や高いパフォーマンスを求める場合、適切な負荷をかけるトレーニングが必要
例えば、イチローのようにバットを何万回も振ることで特定の筋肉が発達することはありますが、全身の筋力をバランスよく向上させるには追加のトレーニングが必要です。つまり、「自然な動きだけで筋肉がつくかどうか」は、目的次第ということになります。
イチローの考え方とライオン理論の共通点とは
では、イチローが筋トレをしない理由と「ライオン理論」にはどのような共通点があるのでしょうか?
イチローは「筋肉の大きさよりも機能性を重視」
イチローはかつて「筋肉をつけすぎると自分の動きが悪くなる」と発言しています。これは、ボディビルダーのように筋肥大を狙うトレーニングをすると、自分の持ち味である「しなやかでスムーズな動き」が損なわれると考えたからです。
ライオンもまた、持久力よりも瞬発力を重視し、無駄な筋肉は持たない体をしています。「必要な筋肉だけを鍛え、余計な負荷をかけない」 という点で、イチローとライオンのトレーニング哲学は似ているといえます。
初動負荷トレーニングとライオンの動きの共通点
イチローが実践している「初動負荷トレーニング」は、筋肉を柔らかく保ち、可動域を最大限に活かすトレーニングです。これは、ライオンがしなやかに動くために柔軟な筋肉を持っているのと似ています。
ライオンは狩りの前にストレッチのような動きをし、狩りが成功した後は長時間リラックスします。「筋肉を鍛えるだけでなく、緩めることも大切にする」 という点で、イチローのトレーニング理論と一致している部分があります。
イチロー流の体づくりを実践する方法

初動負荷トレーニングの具体的なメニューとやり方
イチローが長年取り入れている初動負荷トレーニングは、一般的な筋力トレーニングとは異なり、関節の可動域を広げ、柔軟性や神経系の働きを向上させることを目的としたトレーニング方法です。彼が通うワールドウィングでは、このトレーニング専用のマシンを使って、よりスムーズで自然な動きを引き出すことに重点を置いています。
具体的なメニュー例
-
上半身の柔軟性向上
-
肩甲骨周りをほぐす「プレスプル」
-
胸椎の動きを改善する「スイングスルー」
-
-
下半身の連動性を高める
-
股関節の可動域を広げる「レッグプレス回旋」
-
ハムストリングの伸縮を促す「シーテッドレッグカール」
-
-
瞬発力としなやかさを鍛える
-
体幹の安定性を向上させる「トルソローテーション」
-
腕の振りをスムーズにする「ショルダープレス回旋」
-
イチローはこれらの動きを反復することで、スイングや走塁のパフォーマンスを向上させています。重いウェイトを扱わず、関節や筋肉を無理なく動かすことで、長く競技を続けられる体を作るのが特徴です。
ワールドウィングエンタープライズ公式ホームページ https://www.bmlt-worldwing.com/
筋トレなしで競技力を向上させる方法|神経系トレーニングとは
筋肉を大きくすることだけが競技力向上の鍵ではありません。イチローは、筋力よりも神経系の発達を重視し、体を効率的に使うためのトレーニングを実践してきました。
神経系トレーニングのポイント
-
反応速度を高める
-
例:視覚刺激に素早く反応する「反射トレーニング」
-
目の前で投げられるテニスボールを瞬時にキャッチする
-
-
動きの精度を上げる
-
例:片足でバランスを取りながらスイングの動作を繰り返す
-
これにより、無駄な力を抜いたスムーズな動きが可能に
-
-
可動域を最大限活用する
-
例:PNFストレッチ(神経と筋肉の協調を高めるストレッチ)
-
これにより、よりスムーズで柔軟な動きを実現
-
これらのトレーニングを行うことで、筋肉の大きさに頼らずに、しなやかで素早い動きを実現できます。
イチローの食事・生活習慣|しなやかな体を維持する秘訣
イチローは体を作るために、トレーニングだけでなく食事や生活習慣にもこだわっています。
食事のポイント
-
朝食:カレー(試合前でもルーティンとして食べ続けた)
-
タンパク質:鶏肉・魚中心(筋肥大ではなく筋肉の質を高める)
-
抗酸化作用のある食品を多く摂取(老化防止・疲労回復)
生活習慣
-
毎日のストレッチと初動負荷トレーニングを継続
-
睡眠の質を重視し、早寝早起きを徹底
-
心の安定を保つためにルーティンを守る
これらの習慣が、40代になっても第一線で活躍できた理由の一つです。
結局、自分は筋トレすべき?しなくてもいい?
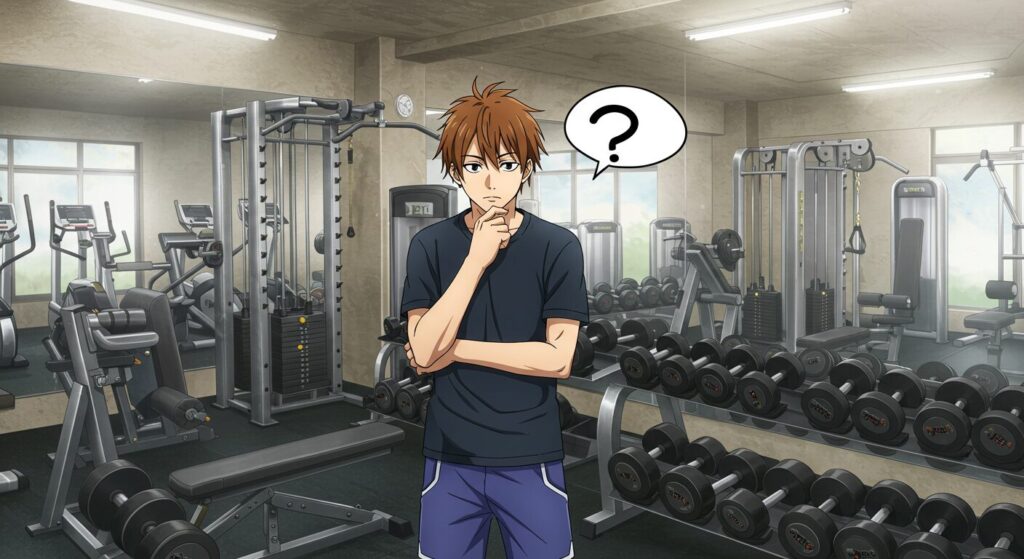
自分の競技・目的に合わせたトレーニング選択の基準
筋トレをすべきかどうかは、競技や目指す体のスタイルによって異なります。
| 競技・目的 | 筋トレ必要度 | 理由 |
|---|---|---|
| 野球(打者) | △ | しなやかさが重要。過度な筋肥大はスイングの邪魔になることも |
| 野球(投手) | ◯ | 球速を上げるための下半身・体幹強化が必要 |
| サッカー | ◯ | 瞬発力とフィジカルコンタクトに備えるため |
| マラソン | △ | 持久力重視、筋肥大は不要 |
| ボディビル | ◎ | 筋肉量が評価基準のため、必須 |
このように、筋トレが必要かどうかは自分の競技や目的によって変わります。
筋トレをやめた場合のリスクと対策
もし筋トレをやめる場合、以下のようなリスクが考えられます。
-
筋力低下によるパフォーマンスの低下
-
関節や腱の耐久力が落ちる
-
姿勢が悪くなることで怪我のリスクが増加
対策として、神経系トレーニングや体幹トレーニングを継続することが重要です。
イチローのような細身でしなやかな体を目指すためにできること
-
初動負荷トレーニングを取り入れる
-
ストレッチや可動域を広げる運動を毎日行う
-
筋トレは最低限に抑え、競技に特化した瞬発力系のトレーニングを重視
-
高タンパク・低脂肪の食事を意識し、過度なカロリー摂取を避ける
-
ルーティンを決めて継続する
これらを意識すれば、無駄な筋肉をつけず、パフォーマンスを最大化できる体づくりが可能になります。
まとめ
-
イチローは「筋トレをしない」と発言していますが、実際には初動負荷トレーニングを取り入れています。
- これは一般的な筋力トレーニングとは異なり、柔軟性や神経系の働きを重視するトレーニングです。
-
筋肉を大きくすることが必ずしもパフォーマンス向上に直結するわけではありません。
- 競技によっては筋肥大が動きを制限し、逆効果になることもあります。
-
筋トレの必要性は競技や目的によって変わります。
- 野球選手でも、パワーが求められる選手としなやかさが重要な選手では適したトレーニングが異なります。
-
イチロー流の体づくりは、初動負荷トレーニングや神経系トレーニング、そして食事・生活習慣の継続が鍵です。
- しなやかで動きやすい体を作るための習慣が、長年の活躍を支えてきました。
-
結局、筋トレをすべきかどうかは「自分の目的次第」です。
- イチローのような体を目指すなら、柔軟性や神経系の鍛錬を意識したトレーニングが有効です。